はじめに:運動ができる子に育てたい!という親の願い
「うちの子、将来スポーツが得意になってほしい」
「いろんな運動ができる、運動神経のいい子に育てたい」
子どもを育てる中で、こうした願いを抱いたことのある方は多いのではないでしょうか?実際に、幼少期の運動経験は、将来の運動能力や体力に大きな影響を及ぼすことが、さまざまな研究で明らかになっています。
この記事では、「どうすれば子どもをスポーツ万能に育てられるのか?」をテーマに、運動神経の正体から、親が家庭でできること、成長段階ごとのポイントまでを徹底解説します。
運動神経は「センス」ではなく「経験」でつくられる!
まず大前提として知っておきたいのは、「運動神経=生まれつきの才能」ではないということです。
運動神経とは医学的には、脳や脊髄から筋肉へと信号を送る運動指令のネットワークのこと。
このネットワークは、子どもの頃に多様な動きを経験することで発達していきます。
つまり、運動神経は「育てるもの」なのです。
実際、トップアスリートの多くは、幼少期に複数のスポーツを経験しています。一つの競技に特化するのは中高生以降でも遅くありません。それまでは「遊びながら動く」「いろんな運動を楽しむ」ことが、将来的な“運動万能”につながるのです。
子どもをスポーツ万能にするための5つのステップ
ゴールデンエイジを活かす(5〜12歳が勝負!)
「ゴールデンエイジ」と呼ばれる5歳から12歳の時期は、神経系の発達が最も活発になります。
この時期にどれだけ多くの運動経験を積んだかが、将来の運動能力のベースになります。
たとえば、
- ジャンプ・走る・止まる・しゃがむなどの基本動作
- ボールを投げる・打つ・蹴るなどの用具操作
- 平衡感覚を使ったバランス動作(スキップ、ケンケン、平均台)
これらを遊びの中で自然に取り入れることが大切です。
特定の競技に絞らない!いろいろな動きを経験させよう
「うちの子はサッカーだけやってます!」という家庭も多いですが、幼少期に特定の種目に絞りすぎるのはリスクもあります。
特定の筋肉や動きばかりを使うことで、偏った身体の使い方が癖になったり、怪我のリスクが高まったりするからです。
サッカーだけでなく、水泳、体操、バレエ、スキー、野球、ダンスなど、多様な動きを経験することが運動能力の基盤になります。
「遊び」と「感覚」を重視した運動を
ただ走らせる、ただジャンプさせるのではなく、「遊びの中で自然と動く」ことが重要です。
たとえば、
- 鬼ごっこ(方向転換・判断力)
- だるまさんがころんだ(反射神経)
- 障害物リレー(バランス感覚)
- けんけんぱ(リズム感・脚力)
こうした遊びは、単に体を動かすだけでなく、「見て→判断して→体を動かす」という運動神経のプロセスを刺激します。
「親子で一緒に楽しむ」ことが最大の秘訣
子どもにとって最も身近なロールモデルは親です。親が運動を楽しんでいる姿を見せることで、子どもも自然と体を動かすようになります。
週末に一緒に公園で遊ぶ、キャッチボールをする、家でダンス動画を見ながら一緒に踊る…
そんなちょっとした時間が、子どもの運動能力に大きな影響を与えます。
失敗を責めず、「できた!」をたくさん体験させる
子どもは成功体験によって自信をつけていきます。
逆に「なんでできないの?」「またミスしたじゃん!」と責めると、運動そのものが嫌いになる原因になります。
小さなできた!をたくさん褒め、「うまくできなくてもいいよ。楽しもう!」という雰囲気づくりが大切です。そうすることで、子供は色んなことにチャレンジするようになります。
成長段階別:スポーツ万能になるためのポイント
幼児期(3〜6歳)
- 運動=遊びの延長。ルールのあるスポーツより、自由に動くことを重視。
- ボール遊び、縄跳び、坂道ダッシュ、砂場の登り降りなど。
- この時期に体の使い方を覚えると、その後の動きが滑らかになります。
小学生前半(6〜9歳)
- 神経系の発達がピーク。多様な動きを経験させる絶好のチャンス。
- 水泳、体操、スキー、サッカーなど、いろんなスポーツに触れさせる。
- 反射・判断・バランスを重視した「複雑な遊び」が効果的。
小学生後半(10〜12歳)
- 少しずつ技術練習も可能に。スポーツの基本スキルを教えるタイミング。
- チームスポーツなどで協調性や戦術理解も育ってくる。
- スポーツ少年団やスクールに通うなら、無理のない頻度で。
- 考えて身体を動かすことを覚える。転んだ時になんで転んだのか。上手くできたときになんで上手く出来たのか。考えることを練習しましょう。
スポーツ万能な子は「脳」も育っている!

運動ができる子は、実は脳の発達も進んでいることが最近の研究で明らかになっています。
- 運動は「前頭前野(判断・集中)」を活性化
- バランス運動は「小脳(運動の調整)」を刺激
- 複雑な動きは「感覚統合(見る・聞く・動くを統合)」を高める
つまり、運動能力が高い子は、「賢く体を使える」だけでなく、「考える力」「集中力」「切り替えの速さ」など、学力にも通じる脳の力が育っているのです。
よくある疑問Q&A
Q. うちの子、運動が苦手ですが才能ないんでしょうか?
A. いいえ。運動が苦手なのは、単に「経験が少ないだけ」の可能性が高いです。
遊びやスポーツを楽しいと感じられれば、徐々に動きは洗練されていきます。
Q. 特定の競技に早くから集中した方がいいのでは?
A. 小学生のうちは広く浅くでOKです。特定競技に集中するのは中学以降がベストです。
Q. 何もしなくても運動神経がいい子っていますが、何が違うんですか?
A. 幼少期からたくさん体を動かしていたことが多いです。才能より「遊びの質と量」が違います。
まとめ:スポーツ万能な子は“育てる”ことができる!
「うちの子をスポーツ万能にしたい!」
その願いは、正しい知識と環境があれば十分に叶えられます。
ポイントは以下の5つ:
- ゴールデンエイジを活かし、運動経験を積ませる
- 特定の競技に絞らず、多様な動きを取り入れる
- 遊びの中で自然と動かせるようにする
- 親も一緒に楽しみ、体を動かす習慣を共有する
- 成功体験を通じて「動けること=楽しい!」と感じさせる
スポーツ万能な子に育てるためには、「うまくさせる」ことより「楽しませる」ことがカギです。
今日からできる一歩を、ぜひ親子で楽しみながら始めてみてください!
〇関連記事


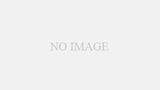
コメント