はじめに
昔の人は当たり前のように地べたにしゃがんで作業をしていました。畑仕事、洗濯、トイレ、食事など、生活の中で「しゃがむ姿勢」はごく自然なものでした。
しかし現代では、「うんこ座り(しゃがみ込み)」ができない人が増えています。
しゃがむと後ろに倒れてしまう、かかとが浮く、膝や股関節が痛む――こうした人は年齢に関係なく多く見られます。
では、なぜ現代人はしゃがめなくなっているのでしょうか?
この記事では、整形外科・運動学・解剖学的な観点からその原因を掘り下げ、さらに改善のためのアプローチを紹介します。
「うんこ座り」とはどんな姿勢?
しゃがみ込み姿勢の特徴
いわゆる「うんこ座り」とは、

- 足底全体(特にかかと)が地面についたまま
- 股関節・膝関節・足関節が深く曲がった状態
- 背中をやや丸めながら、重心が安定している
という姿勢です。
バランスを取るには、足首・膝・股関節・体幹が連動し、骨盤と脊柱の柔軟なコントロールが必要になります。
つまり、単純に「足首が硬い」というだけでなく、全身の協調性が求められる姿勢なのです。
しゃがめない人が増えている理由
最大の要因:足関節の背屈制限
しゃがみ込み姿勢をとるには、「足関節の背屈(足首を前に倒す動き)」が欠かせません。
しかし現代人は、
- 長時間の座り姿勢
- 靴文化(特にヒールや厚底スニーカー)
- デスクワークによる下肢筋の低活動
などの影響で、下腿三頭筋(腓腹筋・ヒラメ筋)やアキレス腱が短縮し、足首の可動域が制限されている人が多いのです。
股関節・膝関節の可動域制限
しゃがむには、
- 股関節の屈曲(約120°)
- 膝関節の屈曲(約130°)
が必要です。
しかし、運動不足や加齢、座位中心の生活によって筋肉や関節包が硬くなり、屈曲可動域の減少が起こります。
特に大腿四頭筋(太もも前面)や腸腰筋の短縮は、股関節の屈曲を妨げ、骨盤が後傾しにくくなります。結果、しゃがもうとすると重心が後方にずれて倒れてしまうのです。
バランス能力・体幹筋力の低下
しゃがみ姿勢では、重心が低く、かつ小さな支持基底面(足裏)内に収まる必要があります。
体幹の安定性が低いと、わずかな重心のズレでバランスを崩しやすくなります。
つまり、コアマッスル(腹横筋・多裂筋など)の機能低下も「しゃがめない」原因の一つです。
姿勢習慣の変化
昔は日常動作の中でしゃがむ機会が多く、関節や筋肉が自然にその可動域を保っていました。
一方、現代では
- 椅子生活中心
- トイレも洋式
- 靴を履いたままの生活
となり、「しゃがむ」という動作そのものが生活から消えつつあります。
つまり、使わない可動域は衰えるのです。
遺伝的・構造的な要因
骨格や関節構造にも個人差があります。
特に、脛骨と距骨の形状、アキレス腱の長さ、骨盤の傾きなどが関係します。
生まれつき足首の背屈が少ない人や、膝蓋骨の可動性が低い人は、訓練してもしゃがみ込みが難しい場合があります。
医学的に見る「しゃがみ込み不能」
整形外科では、「しゃがみ込みテスト(squat test)」を可動域・筋力・疼痛評価として使います。
しゃがめない場合、以下のような疾患が隠れていることもあります。
| 原因 | 主な疾患・障害 |
|---|---|
| 関節の制限 | 足関節拘縮、変形性膝関節症 |
| 筋肉の短縮 | アキレス腱短縮症、ハムストリング硬縮 |
| 神経要因 | 下肢末梢神経障害、脊柱管狭窄症 |
| バランス要因 | 加齢性平衡障害、前庭機能低下 |
特に高齢者では「しゃがめない」ことが転倒リスクや歩行能力低下の指標にもなります。
しゃがむために必要な可動域と筋活動
しゃがみ姿勢では、下肢三関節(股・膝・足)が連動します。
理学療法学的には、以下の関節角度が理想とされます:
| 関節 | 必要な角度 | 主に働く筋肉 |
|---|---|---|
| 足関節背屈 | 約20° | 前脛骨筋・腓腹筋(伸張) |
| 膝関節屈曲 | 約130° | 大腿四頭筋(伸張)・ハムストリング(収縮) |
| 股関節屈曲 | 約120° | 大殿筋(伸張)・腸腰筋(収縮) |
つまり、「しゃがめない」原因は単一ではなく、複数の関節制限と筋バランスの崩れが重なって起きているのです。
しゃがみ込みを改善するためのトレーニング
足首の柔軟性アップ
● アキレス腱ストレッチ
壁に手をついて前後に脚を開き、後ろ脚の踵を床につけたまま体を前方へ。
ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)をしっかり伸ばします。
● 足首背屈モビライゼーション
膝を曲げた状態で足首を前方に押し出す動作。
距骨の可動を促し、しゃがみやすくします。
股関節・膝の柔軟性トレーニング
● ディープスクワットストレッチ
肩幅よりやや広く足を開き、踵をつけたままゆっくりしゃがむ。
背中を丸めず、両肘で膝を外側に押すと股関節が開きやすくなります。
● ハムストリングと殿筋のストレッチ
座位や仰向けで太もも裏・お尻の筋肉をゆっくり伸ばすことで、骨盤の動きを滑らかにします。
体幹・バランスの強化
しゃがみ姿勢では体幹の安定が不可欠。
- プランク(腹横筋)
- デッドバグ(多裂筋)
- バランスボードや片脚立ち
これらを組み合わせることで、下肢と体幹の協調性を高められます。
しゃがめるようになると何が良いのか?
- 歩行や階段動作がスムーズになる
- 下半身の柔軟性・血流改善
- 腰痛や膝痛の予防
- 日常生活動作(床からの立ち上がり)の向上
しゃがみ動作は、実は“人間本来の動き”のひとつ。
これができるということは、関節・筋肉・神経が正常に連携している証拠でもあります。
注意点:無理は禁物
関節炎や半月板損傷など、痛みを伴う人は無理な深いしゃがみは避けましょう。
可動域は少しずつ広げ、痛みや違和感があれば理学療法士や整形外科医に相談することが大切です。
まとめ
現代人が「うんこ座り(しゃがみこみ)」できなくなっているのは、
- 足首・股関節の柔軟性低下
- 体幹バランス能力の低下
- 座位中心の生活習慣
が主な原因です。
しゃがめる身体は、単なる柔軟性だけでなく、身体の統合的な健康指標です。
ストレッチや可動域運動を取り入れ、足から全身を整えることで、“本来の動き”を取り戻していきましょう。

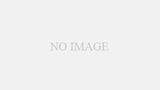
コメント