はじめに
腰痛の原因にはさまざまなものがありますが、中高年の方に特に多いのが「腰椎圧迫骨折」です。骨粗しょう症などによって骨が弱くなった状態で、転倒やくしゃみなどのちょっとした衝撃で起こることもあります。この記事では、腰椎圧迫骨折の基本から、症状、診断方法、治療、リハビリ、再発予防までを詳しく解説します。
腰椎圧迫骨折とは?
腰椎圧迫骨折とは、腰椎(腰の部分にある脊椎の一部)が縦方向からの力で押しつぶされ、つぶれるように骨折することをいいます。骨の強度が保たれていれば通常では起こりにくい骨折ですが、骨粗しょう症などで骨が脆くなっていると、ごく軽い衝撃でも骨折を起こします。
特に第1腰椎(L1)や第2腰椎(L2)に起こりやすく、高齢女性に多いのが特徴です。
原因
腰椎圧迫骨折の主な原因は次の通りです。
骨粗しょう症
圧倒的に多い原因です。加齢に伴い骨密度が低下し、骨がもろくなることで発症します。閉経後の女性は特にリスクが高く、転倒や重いものを持ち上げるなど、日常の動作でも骨折に至ることがあります。
外傷
高所からの転落や交通事故など、強い衝撃が加わることで起こることもあります。若年層ではこのタイプの骨折が多く見られます。
がんの骨転移
がんが腰椎に転移すると、骨が脆くなり骨折を引き起こすことがあります。
症状
腰椎圧迫骨折では、以下のような症状が現れます。
- 突然の腰痛(特に前屈や立ち上がりで強くなる)
- 背中や腰の変形(猫背になることも)
- 動作時痛(歩行や寝返りで痛む)
- 安静時の痛み(進行すると安静にしていても痛みが出る)
- 身長の低下(複数の椎体がつぶれることで起こる)
初期段階では「ぎっくり腰」と間違われることもあり、発見が遅れることがあります。
診断方法
腰椎圧迫骨折の診断には以下の検査が行われます。
X線(レントゲン)検査
最も基本的な検査で、椎体の高さの減少や変形を確認します。典型的なくさび形の変形が見られます。
MRI検査
骨折の新しさ(急性か陳旧性か)や骨髄浮腫の有無を確認するのに有効です。神経への影響も評価できます。
CT検査
椎体の骨折の形状を詳しく確認したいときに用いられます。
骨密度検査(DEXA法)
骨粗しょう症の診断と重症度の評価に用いられます。
治療法
腰椎圧迫骨折の治療は、症状の程度や原因、患者の年齢・状態によって異なります。
保存療法(非手術)
安静とコルセット
急性期には痛みを和らげるため、一定期間の安静が必要です。同時に、腰部を固定するためにコルセットを装着します。これにより、骨の変形進行を抑え、疼痛を軽減します。
薬物療法
- 鎮痛薬(ロキソニン、アセトアミノフェンなど)
- 骨粗しょう症治療薬(ビスホスホネート、活性型ビタミンD、テリパラチドなど)
リハビリテーション
急性期を過ぎたら、筋力の低下や廃用症候群を防ぐために、徐々に体を動かすようにします。理学療法士による指導で、正しい起き上がり方や歩行訓練を行います。
手術療法
保存療法で改善しない場合や神経症状が強い場合は、手術が検討されます。
経皮的椎体形成術(BKP、VP)
骨セメントを椎体内に注入し、椎体を安定化させる低侵襲手術です。短時間で済み、痛みの早期改善が期待できます。
固定術(インストゥルメンテーション)
重度の変形や不安定性がある場合には、金属プレートやスクリューで固定する手術が行われます。
リハビリと日常生活の注意点
腰椎圧迫骨折の回復にはリハビリが重要です。
リハビリの目的
- 筋力低下の予防
- 正しい姿勢の習得
- 転倒予防
- 日常生活動作(ADL)の改善
日常生活での注意
- 急な動きや前かがみを避ける
- コルセットの正しい装着
- 椅子に座るときは背もたれのあるものを使う
- 立ち上がるときは両手で支える
- 十分なカルシウム・ビタミンDの摂取
再発予防
腰椎圧迫骨折は、一度起こすと再発リスクが高いことが知られています。以下のような予防が大切です。
骨粗しょう症の治療
医師の指導のもと、継続的に薬物療法と定期検査を行いましょう。
転倒予防
- 室内の段差や滑りやすい床に注意
- 夜間の照明確保
- 筋力・バランスの維持
運動療法
ウォーキングや軽い体操など、骨に適度な負荷を与えることで骨密度の低下を防げます。
まとめ
腰椎圧迫骨折は高齢者に多く、骨粗しょう症が背景にあることがほとんどです。突然の腰痛が現れた場合は、ただの筋肉痛やぎっくり腰と軽視せず、医療機関を受診することが大切です。早期診断と適切な治療、再発予防の取り組みによって、生活の質を保ちながら回復を目指すことができます。
骨の健康を保つためには、日頃からの運動習慣や栄養管理、そして骨密度のチェックが重要です。腰椎圧迫骨折を防ぐことは、寝たきりや要介護状態の予防にもつながります。ぜひこの機会に、自身の骨の健康について見直してみましょう。
腰が痛い場合はむりしないことが一番です。腰は体の中心なので大切にしましょう。
どうしても動く場合はコルセットしておくと良いかもしれませんね。

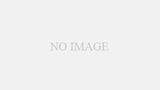
コメント