はじめに
「股関節が引っかかるように痛い」
「長時間歩いた後に鈍痛がある」
「脚の動かし始めに違和感がある」
こうした症状が続く方は、**股関節の関節唇損傷(かんせつしんそんしょう)**の可能性があります。
関節唇損傷は以前まではあまり注目されていませんでしたが、MRIや関節鏡技術の進歩により、見逃されがちな股関節の原因不明の痛みの正体として知られるようになりました。
本記事では、股関節関節唇損傷の原因・症状・診断・治療・リハビリ・予防までを総合的に解説します。股関節の不調に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
関節唇とは?
股関節は、骨盤側の「寛骨臼(かんこつきゅう)」と大腿骨の「骨頭(こっとう)」で構成される球関節です。
この寛骨臼の周囲には、「関節唇(かんせつしん)」という軟骨の一種が存在します。関節唇は線維軟骨でできており、以下のような役割があります。
- 関節の安定性を高める(骨頭を包み込むように支える)
- 衝撃を吸収する
- 関節液を保持して潤滑を保つ
この関節唇が裂けたり、傷ついた状態が
「股関節関節唇損傷」です。
原因
関節唇損傷の原因は、大きく以下の3つに分類されます。
外傷性(スポーツや事故)
- ジャンプの着地時の衝撃
- サッカーやラグビーなどの激しいコンタクト
- 繰り返される股関節の捻りや屈伸動作
特に若年のアスリートに多く、突然の痛みとして発症します。
機能障害性(FAI:股関節インピンジメント)
- 大腿骨の骨頭や寛骨臼の形に異常があることで、関節唇が繰り返し挟まれて損傷する状態。
- 【FAI=Femoroacetabular Impingement:大腿骨寛骨臼インピンジメント】
主に以下の2タイプがあります:
- CAM型:大腿骨頭の形がいびつで関節唇に引っかかる
- PINCER型:寛骨臼が深すぎて関節唇を圧迫する
変性性(加齢・反復動作)
- 加齢や使いすぎによる自然な摩耗
- 40代以降で多く見られ、初期は気づかれにくい
症状
関節唇損傷の主な症状は以下の通りです。
- 鼠径部(股関節の前)の痛み
- 関節のクリック音(ポキッ、コリッ)
- 引っかかり感、ひっかくような痛み
- 動作開始時の痛み(立ち上がり、歩き始め)
- 長時間の座位・歩行後の鈍痛
- 可動域の制限や違和感
痛みは運動時や体重負荷時に増し、安静時に軽減するのが特徴です。初期は軽い違和感程度でも、放置することで症状が悪化し、軟骨損傷や変形性股関節症に進行することがあります。
診断方法
■ 問診と理学所見
- 痛みの場所、発症のきっかけ、活動歴を詳しく確認
- インピンジメント徴候(股関節を内旋・屈曲させたときの痛み)を確認
■ 画像検査
・X線検査
- 関節唇そのものは写らないが、FAIや寛骨臼の異常、関節裂隙の狭小化を確認
・MRI(関節唇損傷の検出に有効)
- 関節唇の損傷や断裂、炎症などを映し出すことが可能
- **MRA(関節造影MRI)**はより高精度で診断可能
・関節鏡検査
- 関節内を直接観察できる手技。診断と同時に治療も行える
治療法
関節唇損傷の治療は、保存療法と手術療法の2本立てです。
■ 保存療法(軽症〜中等症)
安静と活動制限
- スポーツや激しい動作を制限
薬物療法
- 消炎鎮痛薬(NSAIDs)による痛みのコントロール
理学療法(リハビリ)
- 股関節周囲筋の強化(特に中殿筋・腸腰筋)
- 可動域の改善
- 骨盤・体幹の安定性向上
- FAIがある場合、動作指導も重要
→ 保存療法で改善しない場合や、スポーツ復帰を希望する場合には手術が検討されます。
■ 手術療法(関節鏡手術)
- 関節鏡(カメラ)を用いた低侵襲手術
- 関節唇の「縫合」または「部分切除」
- 同時にFAIの骨性病変があれば、削骨処置を行う
術後は入院・リハビリを経て、3〜6ヶ月でスポーツ復帰が目安となります。
術後のリハビリと経過
手術後のリハビリは回復のカギを握ります。焦らず段階的に進めることが大切です。
■ 術後0〜2週
- 松葉杖歩行(荷重制限あり)
- 股関節の可動域訓練(他動から自動へ)
■ 2〜6週
- 徐々に荷重を増やす
- 股関節周囲筋トレーニング開始
■ 2〜3ヶ月
- 低衝撃の有酸素運動(エアロバイク、水中歩行など)
■ 3〜6ヶ月
- 筋力・可動域の回復が進み、スポーツ復帰可能なレベルへ
※再発防止にはフォームの見直しや柔軟性の確保、骨盤・体幹安定性の強化が不可欠です。
予防とセルフケア
関節唇損傷は、予防可能な疾患でもあります。以下の点に注意しましょう。
■ 股関節周囲の筋トレ
- 中殿筋、腸腰筋、大腿四頭筋の強化
- 股関節を安定させることで、負担を軽減
■ 柔軟性維持
- ハムストリングスや内転筋、腸腰筋などのストレッチ
- 可動域の確保は衝撃吸収にもつながります
■ スポーツ時のフォーム指導
- 蹴る、ひねる、ジャンプ動作での体の使い方の改善
- FAIがある場合は早期に専門医へ相談を
■ 日常生活での注意点
- 長時間の座位を避ける
- あぐらや正座など股関節に負荷のかかる姿勢を控える
まとめ
股関節関節唇損傷は、見逃されやすく、慢性化しやすい疾患ですが、早期発見と適切な治療で十分に改善が可能です。
● 要点まとめ
- 股関節の深部痛や引っかかり感があれば要注意
- FAIやスポーツ外傷、加齢が主な原因
- 診断にはMRIや関節鏡が有効

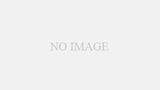

コメント